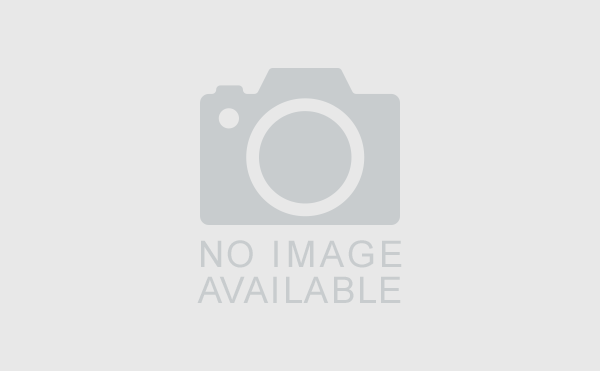”私”から”私たち”へ =「ツボ」③ 達人の力を引き出す!
天草市五和町城河原の公園づくりを通じて気づいたコミュニティやコモンズを広げていくためのツボ、三つ目のツボは「達人の力を引き出す!」です。
今回の公園づくりで、大学生とともに平日から汗を流して下さった地元の方々は主に現役を退かれた60代、70代の方が多かったのですが、皆さん、現役時代に培った技を存分に発揮してくださいました。元製材業者の方は竹や木をチェーンソーで易々と切り倒し、農家の方(今も現役)は杭を打ちこんだり、竹やぶを切り拓いたり、どんな作業も軽々とこなしてくださいました。公園予定地の上の原っぱをショベルカーで整地してくださる方まで‥。一次産業や二次産業が盛んな地方は本当に“人財”が豊富ですね、専門の業者さんにお願いしなくても、いろんなことが実現できてしまいます。
なかでも特に大きな力を発揮してくださったのは、以前、建設業を営んでいた西川和文さん(72)でした。今回の公園づくりでは、ホタルのエサとなるカワニナを増やすためのビオトープ(人工池)づくりと、山神様を祀っている窪地の広場と上の原っぱを安全に昇り降りするための階段づくりという二つのミッションがあったのですが、実はいずれもこれまで造った経験のある人はいませんでした。全員が初心者ということで、どうやって造るか、みんなで知恵を出し合うところから始めました。コンクリートや鉄など人工的なものは使わずに自然にあるもので造るということでまずは合意。その後、現場にたくさんある竹や木を活用して造るという案が出て先行事例などを調べていたのですが、ネックとなったのは維持管理でした。竹は数年で朽ちていくのでそのたびに補修もしくは新たな造り直しが求められます。地域の皆さんの高齢化が進む中で、継続して担っていけるのか、というところで検討はストップ。そんな時、知人から紹介していただいたのが現場から車で15分ほどの隣町でボランティアで公園づくりに取り組んでいる西川さんでした。
西川さんはこれまで20年余りにわたって「かずま園」という公園づくりにコツコツと取り組んでこられました。土木工事で出た石や廃材などを活用して、補助金などは一切使わずに山に道や階段を造り、木や花を植え、展望台を建て、地元の皆さんの憩いの場となる立派な公園を造り上げられました。桜やアジサイなどの花々が季節ごとに咲き誇り、展望台からの眺めはそれはもう見事なものです。
私たちの公園づくりについて相談すると西川さんは早速、翌日には現地に足を運んで、近くの河原の石を使って階段やビオトープを造ることを提案してくださいました。西川さんはまさに石積みの達人です! お会いしたばかりだというのに、大学生の実地指導まで引き受けて下さいました。


こうして大学生は西川さんの助言を受けながら、階段づくりとビオトープづくりに取り組むことになりました。公園予定地は窪地で重機を入れられないので、すべて人力でやらねばなりません。まずは河原の石を天秤棒に乗せ2人1組で肩に担いで運び出します。そして山の斜面を平らに削り石を置いていきます。しっかりと、ぐらつかないよう小さな石や土を間に詰めて固定し、また上の段へ。大学生はいずれも土木工学科で土木について学んではいますが、こうした実地での作業は初めての経験です。西川さんから石を固定させるためのコツを教えていただき、何度もやり直しをしながら、ついには安全に昇り降りできる階段を造り上げることができました。同様にホタルのエサとなるカワニナを育てるためのビオトープ(人工池)も住民の方と力を合わせていくつもの石を積みあげ、見事に造りあげました。


地域の皆さんの憩いの場となるこうした公園の整備は、従来、自治体がやってきた仕事かもしれません。でも、地域の達人の力を借り、みんなで力を出し合えば、行政に頼らなくてもかなりのことができると今回、実感しました。財政難の今、要望しても造ってもらえる確約はありませんし、何より、住民自身が自ら造りあげた公園であれば愛着がわいて利用も広がるでしょう。どんどん手を入れてもっともっと素敵な公園にしていくこともできます。維持管理という作業を通じて、公園が地域の人たちをつなぐ求心力となっていくことも期待できそうです。


今回は公園づくりということで主に土木関係の達人の皆さんの活躍が目立ったわけですが、そうでなくても例えば、野菜づくりの達人、伝統食や保存食づくりの達人、山菜採りの達人、漬け物づくりの達人、陶芸の達人、養蜂の達人、炭焼きの達人など、具体的に私の頭にお名前とお顔が浮かぶ方だけでも、地域にはたくさんの達人の方がいらっしゃいます。ほかにも、おいしいコーヒーを淹れる達人、カレー作りの達人、裁縫の達人、英会話の達人、草花について詳しい方、星空について詳しい方、史跡、歴史について詳しい方等々、何かに秀でた方はたくさんいらっしゃるでしょう。そんな達人を探し出し、地域のために力を活かしていただける仕組みや仕掛けをうまく作れたら、コミュニティのつながりがぐっと強まり、より豊かになれるだろうなと思います。
いま、幼い頃からスポーツや音楽をはじめ様々な習い事に通う子供が多く、民間の調査によりますと未就学児では半数、小学生では8割に上り、この30年で2倍に増えています。習い事に通う率は親の年収に比例して高まり、収入の低い家庭では通いたくても通えない子どももいるなど格差が生まれています。お金でサービスを買うのではなく、地域の中で子どもも親世代もシニア世代もみんなができることを持ち寄って、みんなで楽しみ、みんなで学び合う、それが生きがいづくりにもつながっていく。そんな豊かなコミュニティを作れたら‥。天草から小さな一歩を積み重ねていきたいと思います。
次回も、公園づくりを通じて気づいたコミュニティやコモンズを広げていくための「ツボ」について続きをお伝えします‥。
(代表理事 後藤千恵)